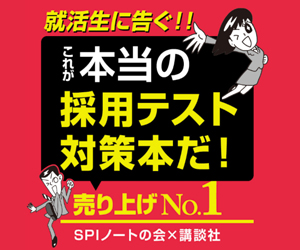内容紹介
+ もっとみる
目次
- 1 塩の道
- 1.塩は神に祭られた例がない
- 2.製塩法とその器具の移り変わり
- 3.塩の生産量の増加に伴う暮らしの変化
- 4.塩の道を歩いた牛の話
- 5.塩を通して見られる生活の知恵
- 6.塩の通る道は先に通ずる重要な道
- 2 日本人と食べもの
- 1.民衆の手から手へ広がっていった作物
- 2.北方の文化を見直してみよう
- 3.稲作技術の広がり方
- 4.人間は食うためにだけ働いているのではない
- 5.食糧を自給するためのいろいろなくふう
- 3 暮らしの形と美
- 1.環境に適応する生活のためのデザイン
- 2.農具の使い方にみる日本人の性格
- 3.直線を巧みに利用した家の建て方
- 4.畳の発明で座る生活に
- 5.軟質文化が日本人を器用にした
- 6.生活を守る強さをもつ美
製品情報
| 製品名 | 塩の道 |
|---|---|
| 著者名 | 著:宮本 常一 |
| 発売日 | 1985年03月06日 |
| 価格 | 定価:1,012円(本体920円) |
| ISBN | 978-4-06-158677-2 |
| 通巻番号 | 677 |
| 判型 | A6 |
| ページ数 | 220ページ |
| シリーズ | 講談社学術文庫 |
関連シリーズ
-

弥勒 宮田登
-

今を生きる思想 宮本常一
-

包み結びの歳時記
-

女神誕生
-

世界の音 楽器の歴史と文化
-

女人禁制
-

日本人の死生観
-

埋もれた日本地図
-

言霊の民俗誌
-

土葬の村
-

日本人の原風景 風土と信心とたつきの道
-

民俗学
-

神主と村の民俗誌
-

江戸東京の庶民信仰
-

日本の古式捕鯨
-

故郷七十年
-

滑稽の研究
-

日本古代呪術
-

霊山と日本人
-

魚の文化史
-

地名の研究
-

東北学/もうひとつの東北
-

物語の中世 神話・説話・民話の歴史学
-

江戸滑稽化物尽くし
-

金枝篇
-

日本の鬼 日本文化探求の視角
-

早川孝太郎 花祭
-

東北学/忘れられた東北
-

ニッポンの奇祭
-

氏神さまと鎮守さま 神社の民俗史
-

「怪異」の政治社会学
-

金太郎の母を探ねて
-

「大東亜民俗学」の虚実
-

風景の生産・風景の解放
-

ニライカナイから届いた言葉 声に出して味わいたいウチナーグチ
-

ももんがあ対見越入道 江戸の化物たち
-

山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰
-

生態と民俗 人と動植物の相渉譜
-

花の民俗学
-

桃太郎の母
-

子守り唄の誕生
-

熊野詣
-

言霊と他界
-

境界の発生
-

蛇
-

神々の精神史
-

憑霊信仰論 妖怪研究への試み
-

民俗学の旅
-

明治大正史 世相篇
-

日本藝能史六講
-

庶民の発見
-

ふるさとの生活
-

民間暦
-

魔の系譜
-

年中行事覚書
-

おとこ・おんなの民俗誌