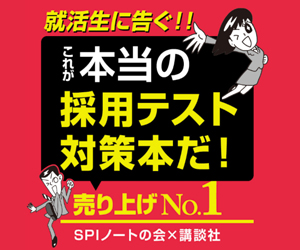内容紹介
+ もっとみる
目次
- プロローグ──ケアマネジャー時代の経験から
- ベランダから部屋に立ち入る/応答のない部屋に立ち入るには/チェーンロックを切って/孤独死はまぬがれたが/ケアマネジャーやヘルパー、民生委員の心情/他
- 第1章 検視医や援助職の立場から──遺体発見の現場
- まず警察を呼ぶ/警察の捜査/検視医の役割/ある検視医の話/発見されるまでの日数が問題/検視について/ケアマネジャー──孤独死に接して1/他
- 第2章 孤独死問題はどう考えられてきたか
- 1970年代の孤独死問題/阪神・淡路大震災/孤独死の定義づけ/東京新聞と新宿区のとらえかた/UR都市機構のとらえかた/団地内の孤独死/他
- 第3章 葬儀業者や遺品整理業者からみた孤独死
- 団地での葬儀展示会/棺の中に入ってみて/孤独死の葬儀/孤独死でお経を読む──僧侶の話/葬儀業界の事情/葬儀の場所/遺品整理業者の役割/他
- 第4章 家族と地域社会の変容と孤独死
- 2015年には21人に1人が独り暮らし高齢者/高齢者世帯の中で独り暮らしや夫婦ふたり暮らしが増えてきた/結婚しない人の増加/熟年離婚/他
- 第5章 家で亡くなる、病院で亡くなる
- 「最期は自宅で」と言っても/歴史をさかのぼると/病院死は政府の政策誘導でこれから減っていく/病院で亡くなったが……という経験/孤独死させてしまったという思い
- 第6章 いま、地域で独り暮らし高齢者を見守るということ
- 孤独死を考える2つの視点──「孤独死させない」と「早く発見する」/松戸市常盤平団地の見守り活動/孤独死ゼロ作戦/独り暮らし高齢者世帯を夜回り/70代が中心の活発な自治会会議/自治会新聞/常盤平団地の成功の理由/民生委員の後任問題/公務員も地域の見守り活動の一翼を担う/町会と民生委員/NPOに市が委託/新聞配達業による見守り/市役所とヤクルトの連携/他
- エピローグ
- 講演後の感想/死後の後始末の自己責任/人とのつながりとは?/被災地の仮設住宅で/買い物、食事、交流の場/行政のバックアップが必要不可欠/地域包括支援センター/公務員なら責任がとれる/「見守る側」を分類して考える/サービスを必要としている人へのアウトリーチ/65歳未満の孤独死対策/死の社会化の時代/政府が唱える「自助」と筆者が考える「自助」の違い
- あとがき
製品情報
| 製品名 | 孤独死のリアル |
|---|---|
| 著者名 | 著:結城 康博 |
| 発売日 | 2014年05月16日 |
| 価格 | 定価:836円(本体760円) |
| ISBN | 978-4-06-288264-4 |
| 通巻番号 | 2264 |
| 判型 | 新書 |
| ページ数 | 224ページ |
| シリーズ | 講談社現代新書 |